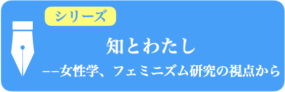
「わたしと知――フェミニズムに出会って」
岡野八代(同志社大学教授・フェミ科研費裁判原告)
強い信念があったわけではありませんが、わたしは、高校時代から、日本社会で役に立つような仕事に就くことはしたくないと思っていました。当時一番好きだったのは、本を読むことでしたから、文学部への進学を望みながら、親との話し合い――女性はきちんと手に職をつけていないと、経済的に困ることになる――で、将来的な展望がじっさいにはあったわけではありませんが、社会科学系の学部を受験し、80年代後半に政治学科に入学しました。今思えば、政治学をしっかりと勉強したからといって、なにか社会に「貢献」できる仕事につけるわけではないのですが、政治学科にいながら、なるべく、当時のわたしは、あくまで自分の基準で「役に立たない」と思える科目を受講していました。とはいえ、政治学科を卒業するためには、一定の単位数以上の政治学系の科目を取得しなければなりませんでしたし、なにより、3年次より始まるゼミは、当然ですが政治学関連のゼミしかありませんでした。
そのなかで、当時のわたしが最も「役に立たない」と考えたのが、西洋政治思想史でした。
西洋政治思想史は、哲学者たちが政治とは何かをめぐり論じてきた、その歴史についての研究です。大学3年生となり、ゼミで最初に読んだテキストは、『ソクラテスの弁明』でした。ソクラテスは、ご存知の方も多いように、古代アテネで、〈正しいこととはなにか知っていますか?〉と聞いて回り、みなが知っているといいながら、結局は何も知らなかったということを発見する哲学者です。そして、自分だけが知らないということを知っている点で他のみなとは違うと、「無知の知」という、知を愛する者たちの心の中に刻まれる有名な言葉を残しました。
哲学は、英語でPhilosophyですが、これは文字通り知を愛するという意味です。知を意味するSophiaと、愛を意味するPhilosからできた言葉です。知とは物事の自然、本質を見極めようとする営みです。ソクラテスのような哲学者が誕生する以前には、事物や現象を慣習によって区別していました。したがって、正しいことは、伝統や慣習、そしてその時代の法律によって決まっているのだと考えられました。それに対して、ソクラテスに始まる哲学者は、時代や地域によって左右されない正しさがあるはずだとして、何世紀にもわたり、議論を尽くしてきました。したがって、政治思想における一大テーマである正義論は、〈自分だけが正しい〉、あるいは〈正義を振りかざして、他の意見を認めない〉といったよくある中傷とは、まったく逆の議論です。知を愛する者として、常識で語られている正しさや、とりわけ権力者たちが振りかざす正義を疑うことから、哲学は始まっているからです。
|
フェミ科研費裁判支援の会では、私たち一人ひとりにとっての知を考えるために、「知とわたし――女性学、フェミニズム研究の視点から」というテーマでエッセイを募集します。本裁判に注目してくださっている皆さまのエッセイや体験談をお待ちしています(タイトル、文量などは自由です)。投稿は、支援の会メールアドレス(info@kaken.fem.jp)まで。ハッシュタグ「#知とわたし」でもエピソードを募集しています. |
哲学に限らず、物事の本質を見いだしたいという思いにかられる研究は、皆が見ていると思っているもの、社会で当たり前のように通用していることを、まずは疑うことから始まります。政治思想においては、人間社会にそもそもなぜ政治が必要なのか、権力と暴力は同じなのか、法律の根源になにがあるのか、といったことを考えようとしてきました。それゆえ、当時の人びとが信じていたことを疑ったソクラテスは、アテネの若者をたぶらかしたという理由で、死刑が言い渡されます。それが、『ソクラテスの弁明』がプラトンによって書かれた背景です。あまり社会の役に立つことはしたくないと考えていたわたしに、知を愛することと社会で生きることは、どうすれば両立するのかを考えるきっかけを作ってくれたのが、当時のゼミで読んだ政治思想史の古典でした。
わたしがフェミニズムに出会うのは、学部を卒業した後の留学先でした。それまでほとんど男性が書いたものしか読んでなかった、なによりも、政治学科で男性の教員からしか講義を受けていなかったわたしに、留学先の教授たちは、自らもフェミニストとして、男性が書いた本について、時代を超えて果敢に挑戦していました。その姿をみて、ずっと「社会の役に立ちたくない」と思っていたときに考えていた「社会」は、当時わたしが眼前にみていた日本社会にすぎないのであって、もし社会が変わるならば、わたしでも何かできることがあるのではと思い直し始めました。はじめて接する女性の研究者たちが選ぶ女性の手で書かれたテキスト、「政治」という考えかたそのものを考え直そうとする先生たちの熱い言葉に、わたしは、いまの社会を変えていこう、みなが当たり前と思っているものこそを疑おうという、生きた哲学者をみる思いでした。
彼女たちは、この社会の生き難さをはっきりと捉えるための言葉を探し、そのための知を訪ね歩く、知を愛し求める先輩でした。彼女たちは教師として、わたしに、「この社会」に役立つかどうかではなく、一人ひとりの生き方に力を与える知を作り上げなさい、言葉を獲得しなさい、そうすれば、「この社会」は変わるかもしれないことを教えてくれました。フェミニストたちの言葉はわたしにとって、その格闘の証でした。
たとえばフェミニズムの歴史をひもとくと、「ひとは生まれながらにして自由で平等である」と宣言したフランス革命後のフランスで、人権宣言で言及されている人Homme/ Manとは男性に他ならないと、女性の権利を訴えたオーランプ・ドゥ・グージュは、革命の精神に反しているとして、ギロチンにかけられました。社会や政治が、男性の言葉で彩られているだけでなく、まさに男性しか想定していないことを指摘しただけで、命が奪われた時代があったのです。
知を愛する者は、少し歴史を振り返っただけでも、多数者や権力者が思っていることを疑わざるを得ないわけですから、つねに危険と隣り合わせです。それだけでなく、再度、語源を考えてみると、学者scholarの語源が、余暇やひま、を意味するスコレーから来ていることからも分かるように、学校に通い、学派schoolを作るような人たちには、静かな時間が必要です。つまり、現在であれば、多くの人に課せられている経済活動をする時間がありません。つまり、だれかに経済的には依存しなければならない存在です。
知を愛するひとはしたがって、二重の意味で、社会的には弱い存在ともいえるのではないでしょうか。権力者や冨を持つ者は、その知を、自分たちのために利用しようとするでしょう。兵糧攻めにあえば、知を冨に変えたり、権力者の庇護を受けようとする者も当然でてくるでしょう。そして、日本では、戦前、多くの研究は侵略戦争のために動員され、ときの政治のあり方を批判する研究者は、その職を奪われました。憲法25条の学問の自由が、個人の思想の自由とは分けて、とくに、知を愛する者たちのコミュニティである大学や組織を守ろうとしているのは、学問がもつこの二重の脆弱性のためなのです。
哲学といった言葉は難解に聞こえますが、わたしたち一人ひとりもこの知を愛する人なのだと、わたしは信じています。小さなこどもはつねに、新しい物事に触れるたびに、目を輝かせ、驚き、そして「なぜ?」と聞きます。いまの日本の政治は、よい意味での「なぜ?」でなく、逆に、「どうしてこんなことがおきるのだ?」といった、とても否定的な驚きしかありませんが、それでも、ことの本質、現在の政権で生じている摩訶不思議な事象の奥にあるはずの、現在の政治の真実をわたしたちが問うこともまた、たいせつな知の営みでしょう。
私たちの社会は、いま知り得ないこと、納得しないこと、自分にとっては窮屈だと思うことに対して、おかしい!何故?!と声をあげられることで、これまでになかった可能性を拓いてきました。世界の豊かさに魅了され、感嘆する時間がどんどんと削られていくなかで、金を受け取っているなら文句をいうなといった主張が当たり前の世界になれば、あらゆる学とつく組織が、人間としての喜びを感じられる組織ではなくなるでしょう。いまわたしたちは、驚きや感嘆に満ちた人間性を奪われようとしていると、政治思想史の過去を振り返りながら危機感を募らせています。
本裁判に注目してくださっているどなたでも、エッセイや体験談を是非お待ちしています。
info@kaken.fem.jp
(タイトル、文量などは自由です)
ハッシュタグ #知とわたし でもエピソードを募集しています。
