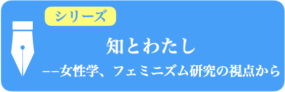
問題意識をもつこと
元橋利恵(フェミ科研費裁判支援の会 事務局)
「人は2つのことを知りたいと思っている。1つは、世界とは何か。もう1つは、自分とは何者か、だ。」
大学生の時にお世話になったある先生の言葉だ。(人文社会系の)学問や研究とは、簡単に言えば、社会や人間に関わる様々に問題意識をもちそれを探求する営みだ。それは「象牙の塔」のイメージにあるような、別世界の住人たちだけに嗜まれるお遊びではない。学問や研究とは、本来誰もがもつ要求から出発していると私が考えるきっかけとなった言葉だ。
だが、大学生当時の私は、問題意識をもつということがどういうことなのかがわからなかった。普通は問題意識とは何か困ったことやトラブルが生じた時に現れる。しかし、当時の私は自分が何に困っているかもわからなかった。決して困っていなかったのではない。自分の困難やいわゆる「生きづらさ」を的確に表現する言葉や理屈、またそれを表現するコミュニケーションや態度を全く獲得できていなかったのだと思う。
それどころか、当時の私は「問題意識をもつ人たち」を冷笑していた。平和や差別の是正を主張したり社会を批判する人たちはスマートでないし、ダサいだとさえ感じていた。それは私自身が、なんだかんだで社会はうまく回っており、「良い人」でいれば、「間違わず」にうまく振舞えていれば全うな人生が用意されるはず、という感覚を強く持っていたからだ。私が大学に入学した2005年は、小泉政権が発足し「自己責任」という言葉が流行した年だ。社会の空気を「間違わず」に読み取り、吸収していた私は、社会に批判的で問題意識を抱く人たちのほうが「間違って」いると思っていたのだ。
そのような素朴な自己責任論信奉者であった当時の私のあり方は、事実を学び受け入れることを拒み、誰かの痛みを想像し「かわいそうだな」「これはおかしいな」「どうすれば寄りそえるかな」と共感するというごく当たり前の感覚を鈍らせることで成り立っていた。それは自分の実感や感情、痛みを否定することでもあった。当時の私は、実は誰よりも不満に満ちていて、「社会は変えられない」「他人は信じられない」という不信と絶望に苛まれていて、何より自分自身を受け入れられずに苦しんでいたように思う。
問題意識をもつということが体感として芯から理解できたのは、女性学という分野の学問を知り、触れたことがきっかけだった。社会学部ではなかった私は、学部生のおわりごろまで女性学やジェンダー論といった分野があることも知らずにいた。女性学やフェミニズム研究は、性や家族、女性たちの営みを学問や研究テーマとして知を蓄積してきたこと、そしてそれらの知は何より女性たちの実感や運動から出発したものであり、そのことによって既存の知のあり方そのものをも問い直してきた。自分は「バカ」で知的な世界にはふさわしくないと思っていた私にとって、このような知との出会いは大きな転換だった。
自分の意見を人に伝えることができずすぐに泣きだしてしまうこと、自分の容姿が醜いと思い悩み傷ついてきたこと、痴漢にあったと当時の彼氏に打ち明けたら、その痴漢の真似をしながら「ほんとは気持ちよかったんでしょ?」と笑われたこと、その彼に「賢くならないで」と言われモヤモヤしたこと、1人ぼっちで3人の子育てをしてきた母が精神的に追い詰められ時には私にも辛くあたっていたこと、父と成績と進路以外の話をしたことがほぼないこと、従弟が自閉症であることがわかり叔母がシングルマザーになったことに親戚中が冷淡だったこと、所属していたサークルで先輩男性と後輩女性がよくカップルになり関係が終わると女性のほうが集団からフェードアウトしていくこと、これらのことに誰も「おかしい」と言わないこと。
辛いとも思ってこなかったが何かがおかしいと忘れられなかったような出来事に初めて言葉があたえられ、自分自身の輪郭ができた感覚があった。そしてそのことで私はうまれて初めて社会の中に自分を位置付けることができた。これは私にとって、自分の生に意味が与えられたといっても言い過ぎでない経験だったように思う。私のこの体験は、顔も知らないたくさんの女性たちが涙や汗や覚悟とともに知を紡いできた上に成り立っているし、知を通じた彼女たちとの共鳴なしには不可能であったと思う。これは政治やビジネスでのコミュニケーションにはできないことだ。
しかしそうはいっても、学問や研究など役に立たないし、学者は特権階級だ(だから税金が彼らに使われているのはおかしい)といった感覚がむしろ「普通」であるというのも痛いほどよくわかる。有名な、ヴァージニア・ウルフの『自分だけの部屋』の一節にもあるように、物事を思索し続けたり書いたりするには、ある程度「ゆとり」や生活の余白のような部分が必要である。生活やお金の不安で心がいっぱいであったり、労働や誰かの世話に追われていたり、1人で落ち着ける空間がないと難しい。そもそも一般企業に就職したり、家事子育て介護を引き受けているとそのような条件を得ることは非常に難しい。なので実際、学問や研究は一握りの恵まれた人たちのもののようになってしまっている。だが、ここで問題化されるべきなのは、多くの人が生活や労働に追われざるを得ず、余白を持てない働き方や資源配分であるはずだ。知そのものに公的な投資をすることを否定するような言説は、私たちが社会や権力に問題意識をもつ力を削ぐことへつながるのではないだろうか。
政府の学術会議の人事への介入とその後の政府に対応は、学問への不信をあおり、知を積み重ねてきた研究者たちの営みを軽視することだ。それは私たちに対して、「何かがおかしい」と感じたり、この社会に対する問題意識をもつなということを意味する。そして、杉田水脈議員がフェミニズム研究を中傷し、「フェミニズム」と検索して科研費をチェックするようにとSNSで呼びかけた行為が象徴するのは、女性学やフェミニズム研究を侮辱し、学問として認めないという圧力が今なお存在し、支持されているということだ。これは私たちが日常的に感じている差別や違和感を表現し、差別や抑圧は何故起こりどのような社会構造がそれを成り立たせているのかを知ろうとし、自分と世界の輪郭をつかもうとする人間としての要求を否定しているといえるのではないだろうか。
このような圧力や社会の流れに対抗するために、女性学やジェンダー、フェミニズム研究がいかに女性たちの日常や実感と学問を架橋してきたか、そもそも知とは私たちを生かすものであってきたのではないか、さらには知とはどのようであるべきかということを皆で問いたいと考えた。そして、1人でも多くの人の「知とわたし」のエピソードを可視化することで、私たちが問題意識をもつことを否定しようとする社会のベクトルに逆らってみたいと思う。
そこで、フェミ科研費裁判支援の会では、「知とわたし――女性学、フェミニズム研究の視点から」というテーマでエッセイを募集したい。学術会議や科学技術に関わる話はそれ自体専門性が高く多くの人には届きにくい。だがこの企画では、この文章でも書いてきたように、私たち一人ひとりにとっての知を考えるためにも、フェミニズムらしく「わたし」を主語にすることからはじめたいと思う。
| フェミ科研費裁判支援の会では、私たち一人ひとりにとっての知を考えるために、「知とわたし――女性学、フェミニズム研究の視点から」というテーマでエッセイを募集します。本裁判に注目してくださっている皆さまのエッセイや体験談をお待ちしています(タイトル、文量などは自由です)。投稿は、支援の会メールアドレス(info@kaken.fem.jp)まで。ハッシュタグ「#知とわたし」でもエピソードを募集しています。 |
